庄内の在来野菜

最近注目を浴びている在来野菜ですが、本長では漬物の素材として創業時から使用しています。
庄内の風土に根ざした在来野菜をご紹介します。
在来野菜



あつみかぶ
出羽庄内の伝統野菜の代表“温海カブ”。化学肥料を使わない原始的な山焼きによる焼畑栽培で育てます。濃い紫赤色をした丸カブで、甘酢漬けにして色と風味を楽しみます。

藤沢かぶ
平成2年当時、鶴岡市藤沢地区の渡会美代子さんがただ一人栽培していた絶滅寸前の藤沢かぶを、地元「荘内日報」の松木記者の報道がきっかけとなり復活しました。栽培が難しく、収穫時も手間がかかる藤沢かぶ。大根に似た形で、細長く上の方の2/3が赤紫色、肉質がやわらかく、食べやすいのが特長です。渡会さんが大切に守り育てた「藤沢かぶ」の種子が藤沢地区の焼畑と下川地区の砂丘地で育てられ、それぞれの特長を生かし、甘酢漬、たまり漬にしています。

小真木大根
小真木大根(こまぎだいこん)は古くから鶴岡市小真木地区で栽培されております。小ぶりで硬く、寒風で乾燥させると独自の歯ごたえと甘みがでます。正月料理のハリハリ漬醤油漬にします。

外内島(とのじま)きゅうり
鶴岡市外内島地区特産のきゅうりです。皮が薄く、少し苦味を感じます。沖縄の「ゴーヤ」と同じ成分です。

鵜渡川原(うどがわら)きゅうり
酒田市だけで栽培されている、欧州系シベリアきゅうりでつけもの専用種。とくにピックルス用として珍重されております。
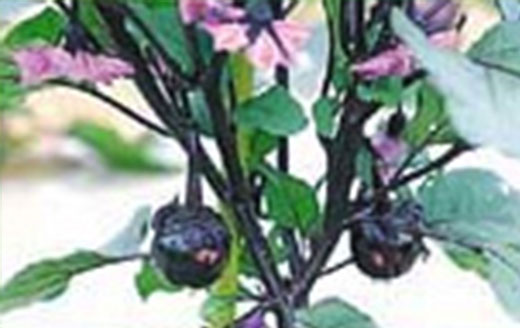
民田なす
鶴岡を代表する夏野菜、丸なすで小粒、肉質がしまって浅漬にもからし漬、粕漬けにも最適です。

沖田なす
鶴岡市朝日地区沖田で栽培されている薄皮なすで、最近知名度があがり、人気もでてきました。沖田なすの特長は皮が薄く、やわらかい、みずみずしい果肉と、苦みやえぐみがなく、ほのかな甘味が感じられるところです。

谷定(たにさだ)孟宗
金峯山の麓で栽培されている柔らかく風味豊かな、日本北限の孟宗。つけもの用としては一番小ぶりな品をつかいます。

だだちゃ豆「尾浦」
夏の鶴岡の味覚を代表するだだちゃ豆。「尾浦」はだだちゃ豆の系統の晩生の品種で、大野博氏が品種改良しました。サヤが大きめでくびれが少なく、味、香り、色もよいので加工に適しています。
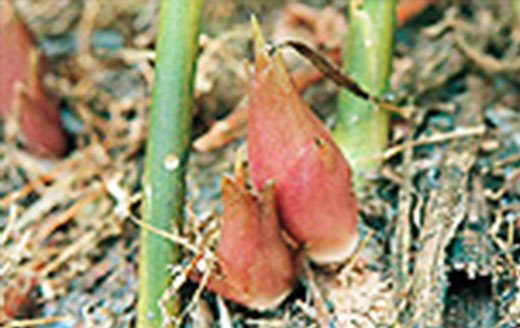
黄金茗荷(こがねみょうが)
暑い夏が終わり、秋の訪れを告げるのが鶴岡市黄金(こがね)地区特産の茗荷です。乾燥・日差しを避けるため庄内柿の木の下で栽培されます。さくさくした歯ざわりと淡い赤い色が特長です。

青菜(せいさい)
山形を代表する越冬野菜です。明治初期に県農事試験場に導入され、山形市を中心に現在では県内一円で栽培されています。特有の辛味と香り、サクッした食感が特長です。
地元の野菜



ふきのとう
残雪の地面から顔を出すキク科の多年草。芳香とほろ苦みがあり細かく刻んで味噌と和えて「ばんげみそ」にします。

しそ
契約しそ畑。広々とした庄内平野のいっかくで良質のしそがとれます。刈り取ったしそはその日のうちに 加工されます。

おばこ梅
酒田市で栽培される「おばこ梅」。肌がきれいで、皮はうすいが肉質がしっかりしてます。木で熟成させ梅干しにします。

うり
粕漬け(奈良漬)専用に開発された「あわみどり」。鶴岡市大山で低農薬、有機栽培を目指して契約栽培をしております。